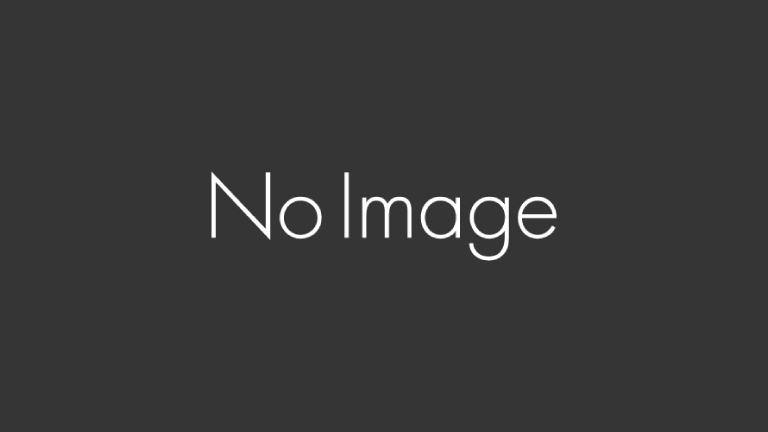✅「炊飯器の保温って、電気代どれくらいかかってるの?」
そんな疑問を感じたことはありませんか?
実は、炊飯器をずっと保温し続けると、電気代がジワジワと家計を圧迫することも…。
しかも、保温しすぎるとご飯の味が落ちてしまったり、思わぬ後悔の声も。
一人暮らしや大家族など、あなたの暮らしに合った「最適なご飯保存術」も紹介します。
読み終えたときには
✅「うちも今日から変えてみようかな」
と思えるヒントが見つかるはずです!
ご飯の保温、どれくらい電気代がかかるの?
炊飯器の保温って本当に電気代がかさむの?
✅1時間、1日、1ヶ月…
知らずに損してるかも。
実際の金額を見て、今すぐチェックしよう!
1時間あたりの保温の電気代は?
炊飯器を使ってご飯を保温していると、電気代が気になりますよね。
実際、1時間保温するとどれくらいの電気代がかかるのでしょうか?
これは炊飯器の種類やメーカー、機種によって異なりますが、一般的に1時間あたりの消費電力…
✅平均で15〜20W程度と言われています。
これを電気料金の目安である1kWhあたり約31円(2025年3月時点の平均)で計算すると、1時間の保温でかかる電気代は約0.5〜0.6円です。
と思うかもしれませんが、これが数時間〜1日中続くと、意外と積もってくるんです。
たとえば、朝炊いたご飯を夜まで保温し続けた場合、約12時間とすると、0.6円×12時間=7.2円。
毎日これを続けると、1ヶ月(30日)で216円程度になります。
ちょっとしたジュース1本分と思うと大したことがないようにも感じますが、節電を意識している方には気になる金額かもしれません。
1日中保温した場合の月額費用は?
では、ご飯を朝炊いてから翌朝まで24時間ずっと保温し続けた場合はどうでしょうか?
✅24時間×0.6円=14.4円
これを30日続けると、月額で約432円になります。
月に400円を高いと思うか、許容範囲と思うかは人それぞれですが…
✅「何気なく毎日保温」
している場合は、トータルで見れば年間5,000円以上の電気代になることも。
「えっ、そんなにかかってるの?」と感じる方も多いと思います。
これは、電気代がじわじわと上がってきている今だからこそ、見直してみる価値があるポイントです。
他の家電と比べて電気代は高いのか?
炊飯器の保温にかかる電気代は、他の家電と比べると決して高い方ではありません。
たとえば、ドライヤー(1200W)を10分使えば約6.2円、エアコン(中程度の運転で600W)を1時間使えば約18.6円になります。
とはいえ、24時間つけっぱなしにしていれば、話は別。
意識しないうちに「チリツモ」で電気代が増えてしまうのは避けたいところですね。
つまり、「短時間なら問題なし」「長時間なら注意が必要」といった感じです。
長時間保温と炊き直し、どっちが得?
ご飯を長時間保温しておくよりも、いったん冷蔵・冷凍保存して、食べるときに電子レンジで温めた方が電気代は安くなるケースが多いです。
たとえば、電子レンジで1膳分(150g程度)を温める場合、600Wで2分程度。
食べるタイミングがわかっているなら、温め直しのほうが安上がりになる可能性が高いですね。
味の違いや手間をどう取るかにもよりますが、節約の観点からは…
✅「炊きたて→冷凍→温め直し」
が一番コスパが良い方法とも言えます。
メーカーや機種で差はあるの?
実は、炊飯器によっても保温に使う電力量にはけっこうな差があります。
たとえば、昔ながらのマイコン式と、最近のIH式、省エネモード搭載モデルでは、消費電力に違いが出てきます。
高機能なモデルでは…
✅「省エネ保温」
✅「高め保温」
✅「エコ保温」
など、保温の方法を選べる機種もあり、これらをうまく使い分けることで、電気代を節約することも可能です。
メーカーの公式サイトや取扱説明書で、保温時の消費電力をチェックしてみると良いですよ。
実際に保温し続けた人の体験談
「保温してたら電気代が予想以上に…」
そんなリアルな声が続々。後悔や発見、体験者だから語れる真実がここにあります!
SNSや掲示板でのリアルな声
炊飯器の保温について、SNSやネット掲示板を覗いてみると、さまざまな声が飛び交っています。
✅「朝炊いたご飯を夜まで保温してるけど、あんまり電気代気にしたことなかった」
という声もあれば…
✅「保温しっぱなしにしてたら、電気代が毎月500円くらい上がっててビックリ!」
という声も。多くの人が「ついついそのままにしてしまうけど、電気代が積もるのは盲点だった」といった意見を投稿しています。
また、「家族全員が食事の時間バラバラだから保温せざるを得ない」という方や、「電子レンジで温めたご飯が苦手で、結局保温派に戻った」など、ライフスタイルに応じたリアルな事情も垣間見えます。
保温しすぎて後悔したケース
とくにX(旧Twitter)やYahoo!知恵袋では、「1ヶ月保温し続けたら電気代いくらだったか?」
などの体験談も多く、それぞれの家庭の使い方によって金額に差が出ることがよくわかります。
炊飯器の保温は便利な機能ですが、「保温しすぎて後悔した…」という声も多く聞かれます。
例えば、ある主婦の方は…
✅「うっかり保温状態のまま2日放置してしまった結果、ご飯が黄色く変色してしまい、変な臭いもしてきたので泣く泣く捨てた」
というエピソードをブログに投稿しています。
また、炊飯器の内釜にこびりついたご飯が取れにくくなり、掃除も大変になったとのこと。
他にも、長時間保温すると水分が飛びすぎてしまい、ご飯がカピカピに。食感もパサパサしてしまい…
✅「結局、捨てることになってしまってもったいなかった…」
という後悔の声がよく見られます。
特に1人暮らしの方や、食べるタイミングが不規則な家庭では…
✅「保温ではなく、冷凍や冷蔵に切り替えるべきだった」
との声が目立ちます。
失敗して初めて気づく「保温しすぎの落とし穴」。少しの工夫で防げることなので、これを読んでいるあなたも、ぜひ保温の時間には気をつけてみてください。
意外と安かった!という声も?
一方で、「保温してても思ったほど電気代はかからないじゃん」と感じている人も多くいます。
特に最近の省エネ型炊飯器を使っている方からは…
✅「1日中保温しても、1ヶ月の電気代が300円程度だった」
という実体験もありました。
ある共働き家庭の男性は、「ご飯を朝に炊いて、夕飯まで保温しっぱなしにしてるけど、電気代はそこまで跳ね上がらない。
電子レンジでチンするよりご飯がふっくらして美味しいから、むしろこっちの方がコスパ良いと感じる」と話しています。
また、「保温時間を12時間以内にしていれば味の劣化も少ないし、炊き直しや冷凍の手間を考えると、むしろ便利で安上がり」といった声も。
最近の炊飯器には「エコ保温」モードや「低温保温」機能が付いているものも多く、これらをうまく使えば、快適さを損なわずに節電も可能です。
つまり、全ての人にとって「保温=損」ではなく、上手に使えばメリットも大きいのです。
家族の人数で違う?電気代の実感
炊飯器の保温による電気代の影響は、家族の人数やライフスタイルによって大きく変わってきます。
たとえば、4人家族で朝・昼・晩と頻繁にご飯を食べる家庭なら、保温している時間も長くなりがち。その分、電気代が気になるケースも多いようです。
一方で、食事のタイミングがある程度そろっている家庭では、炊いたご飯をすぐに食べきることが多く、保温する必要があまりないため、電気代はそこまでかかっていません。
また、一人暮らしの方では「一膳ずつ冷凍してレンチン派」の人が多く、「保温機能はほとんど使わない」という声も多数あります。
これにより、保温による電気代の負担を最小限に抑えることができるわけですね。
このように、同じ炊飯器を使っていても、使い方や家族の人数によって電気代の印象はまったく異なってくるのです。
お米の味の変化とその影響
保温を長時間続けると、味や食感にどんな変化があるのか気になるところですよね。
炊きたてのご飯はふっくらツヤツヤしていて、とても美味しいものですが、6時間、12時間、24時間と時間が経つにつれて、味は徐々に変わってきます。
よくあるのが…
✅「黄ばみ」
✅「パサつき」。
保温時間が長くなると、お米の表面が乾燥し、水分が抜けていきます。
これにより、炊きたてのようなモチモチ感がなくなり、硬くなってしまうのです。
また、お米のデンプンが分解して風味が落ち、特有のにおいが出ることもあります。
さらに、変色が進むと「保温臭」とも呼ばれる独特のにおいが出てしまい、家族から「これ古いご飯?」と不評を買うことも…。
とくにお子さんやグルメなご主人がいる家庭では、味の変化は大きな問題になりがちです。
これらの味の変化に敏感な方ほど、「多少手間でも、冷凍→電子レンジのほうが美味しく感じる」という結果に落ち着くようです。
味とコスパのバランス、あなたはどちらを重視しますか?
節電しながらご飯をおいしく保つ方法
電気代を抑えつつ、ご飯のふっくら感はキープしたい!
そんな願いを叶える、簡単&美味しく保存するテクニックを大公開!
早めに冷凍保存するメリット
ご飯を炊いたあと、なるべく早めに冷凍保存するのは節電の観点からも、おいしさを保つという意味でも非常に効果的な方法です。
保温状態にしておくと電気を使い続けますし、時間が経つとご飯の品質も落ちていきます。
そのため、食べきれない分はすぐに冷凍するのが賢い選択です。
炊きたてのご飯をすぐにラップや保存容器に小分けし、粗熱をとってから冷凍庫へ。
冷凍するタイミングが早ければ早いほど、炊きたてに近い状態をキープできます。
最近は「ご飯専用の冷凍容器」も多く販売されていて、蒸気を逃がさずふっくら感を保てる構造になっているものもあります。
冷凍すれば電気代がかからないだけでなく、食べたい時に必要な分だけ電子レンジで解凍できるので、無駄がありません。
ご飯を冷凍するコツは、「平たくして素早く冷ます」こと。
分厚いままだと中まで冷えるのに時間がかかって食感が悪くなるので、1膳分ずつラップで包んで薄く平らにしておくと良いですよ。
節電もできて、おいしさもキープできる。冷凍保存は、ご飯の新しいスタンダードと言ってもいいかもしれません。
タッパー保存と電子レンジ活用術
冷蔵や冷凍のご飯保存で便利なのが「ご飯専用タッパー」。
普通のタッパーに比べて、蒸気を逃がさずにふっくら仕上がる工夫がされているので、温めたときに炊きたてのようなおいしさを味わえます。
市販されている専用タッパーの多くは、電子レンジ対応で、1食分ずつ分けて保存できるようになっています。
フタをしたまま加熱できるタイプもあるので、忙しい朝や疲れた夜でもワンタッチでご飯が準備できるのは本当に助かります。
また、電子レンジで解凍・加熱する際のポイントは、「ご飯に少しだけ水をふってから加熱する」こと。
これだけで、水分が飛びすぎるのを防ぎ、しっとりもちもちの仕上がりになります。
さらに、加熱時間も重要です。600Wで1分30秒〜2分が目安ですが、タッパーの種類やご飯の量によっては調整が必要です。
ムラなく温めるには、途中で一度取り出してかき混ぜるのもおすすめ。
炊飯器の保温で味が落ちてしまうことに悩んでいた方には、この方法はまさに救世主!
ご飯の保存とおいしさ、そして電気代を両立したいなら、タッパー+電子レンジの組み合わせは鉄板です。
タイマー機能で保温時間を短縮
炊飯器にある「予約タイマー」機能をうまく活用することで、保温時間を大きく減らすことができます。
たとえば、朝7時に起きて朝ご飯を食べるなら、炊飯器のタイマーを「朝6時半」にセットすれば、起きたときに炊きたてのご飯が完成。
無駄な保温時間をカットできます。
夜ご飯用の炊飯も、帰宅時間に合わせてタイマー設定をしておけば、夕方にはホカホカのご飯が炊き上がっています。
「朝に炊いて保温で夕飯までキープ」というやり方をやめれば、1日で数時間分の電気代を節約できます。
最近の炊飯器は「かしこいタイマー調整」ができる機種も多く、炊き上がり時間だけでなく、炊き始めの時間を自動で計算してくれるものも。
こうした機能を活かすことで、手間なく節電が可能になります。
また、週末にまとめて炊飯して冷凍する「一括炊き&冷凍ストック作戦」もおすすめです。
平日は電子レンジでチンするだけなので、毎日炊飯器を動かすよりも手軽で経済的。
タイマー機能は、うまく使えば「手間なし・節電・美味しさキープ」の三拍子がそろう便利機能。
まだ使っていない人は、ぜひ試してみてください。
保温しないご飯の保存グッズ紹介
保温しなくてもご飯をおいしく保存できる便利なグッズが、いま注目されています。
その代表格が「ご飯用真空保存容器」や「炊きたて風冷蔵保温ケース」。
これらは、ご飯の酸化や乾燥を防ぎつつ、冷蔵庫での保存にも対応しているアイテムです。
中でも人気なのが「おひつ型保存容器」。炊きたてご飯を入れてそのまま食卓に出せるデザインで、冷めても風味が落ちにくく、見た目もおしゃれ。
陶器製や竹製のものもあり、自然素材がご飯の湿度を調整してくれます。
また、冷凍用には「シリコン製の一膳保存容器」や「電子レンジ対応の密閉タッパー」が便利。
ラップよりもエコで、洗って繰り返し使えるのも嬉しいポイントです。
保温をやめてこうした保存グッズを使うだけで、電気代の節約はもちろん、食卓も少しグレードアップします。
「おいしさ」と「節約」を両立したい方には、ぜひ取り入れてほしいアイテムです。
炊き上がりのご飯を美味しく保つコツ
最後に、炊きたてのご飯をよりおいしく保つための工夫も紹介しておきます。
ちょっとしたことですが、これを知っているだけで、ご飯の味がワンランク上がります。
まず大切なのは、炊飯後すぐに内釜のご飯をしゃもじで切るように混ぜること。
これにより、余分な水分が飛び、ベチャっとした食感を防げます。
次に、ご飯を容器に移すときは、なるべく早めに空気に触れさせて熱を飛ばすようにしましょう。
密閉状態で熱いまま保存すると、蒸気がこもって水っぽくなったり、雑菌の繁殖リスクが高まったりします。
また、冷凍する前には「ご飯を薄く広げる」ことで、冷凍&解凍のムラを防ぎ、炊きたてに近い食感を保つことができます。
保温に頼らず、ご飯をおいしく保つには、こうしたちょっとした工夫が鍵になります。
美味しさと節約、どちらも手に入れるための知恵として、ぜひ覚えておきましょう。
最新の炊飯器は電気代が安いって本当?
昔の炊飯器と全然違う!
最新モデルは驚くほど省エネで高性能。買い替えで電気代もご飯の味も劇的に変わる理由とは
省エネ炊飯器の特徴とは?
最近の炊飯器は、昔に比べて格段に「省エネ設計」が進んでいます。
一番の特徴は、保温モードの電力消費を大幅に抑える工夫がされている点です。
たとえば、最新モデルの多くは「エコ保温」「低温保温」「間欠保温(オンオフを自動切替)」といった機能が搭載されており、無駄な電気の使用を抑えつつ、ご飯の品質を保つように作られています。
また、内釜の構造も進化しており、熱効率の高い素材(多層構造・銅・炭釜など)を使用することで、少ないエネルギーでしっかり加熱・保温ができるようになっています。
炊飯中もAIによる「火加減調整機能」や「吸水コントロール機能」などが導入されており、無駄なく賢く炊き上げるのが今どきの炊飯器。
こうしたテクノロジーの進化が、電気代の節約に繋がっているのです。
つまり、古い炊飯器をずっと使っている方は、最新モデルに買い替えることで「味」も「節電」も両方手に入る可能性が高いというわけですね。
IH式とマイコン式で電気代は違う?
炊飯器には大きく分けて「マイコン式」と「IH式」の2タイプがありますが、実は電気代に差が出るポイントでもあります。
マイコン式は、底のヒーターだけで釜を温める方式で、構造がシンプル。そのため本体価格は安いですが、加熱ムラが起こりやすく、長時間の保温では電気を多く消費してしまう傾向があります。
一方、IH式(電磁誘導加熱)は釜全体を包み込むように加熱するため、熱の伝わり方が均一。
加熱効率が高く、短時間で炊飯や保温ができるため、電気代の節約につながる場合が多いです。
さらに、保温中も全体をじんわりと一定温度でキープできるので、ご飯の味も落ちにくいというメリットがあります。
ただし、IH式は初期費用が高めになるため、「長期的な電気代と味の安定性をとるか」「本体価格の安さを重視するか」で選ぶと良いでしょう。
エコモードの活用方法
最新炊飯器に搭載されている「エコモード(省エネモード)」は、電気代を抑えたい方にとって強い味方です。
このモードを使うと、炊飯時や保温時の加熱時間や温度を自動で調整し、必要最低限の電力で運転してくれます。
たとえば、炊飯中の加熱温度を少しだけ下げたり、保温温度を通常より2~3度下げるだけでも、電気代の節約につながるんです。
ご飯の味にそこまでこだわりがない場合や、短時間の保温で済む場合には、このエコモードがぴったり。
また、エコモード使用中は炊きあがりに若干の違いが出る場合がありますが、「そこまで気にならない」「むしろふっくらして美味しい」と感じる人も多いです。
一部の炊飯器では、ユーザーの炊飯習慣を学習して、自動的にエコな炊き方を提案してくれるAI機能も搭載されています。
使わない手はありません!
人気メーカー別省エネモデル比較
では、実際にどのメーカーの炊飯器が省エネに優れているのでしょうか?
ここでは、特に人気のある3社を例に、代表的な省エネモデルを比較してみましょう。
| メーカー | モデル名 | 特徴 | 1時間あたりの保温消費電力 | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|
| 象印 | 極め炊き NP-XB10 | エコ保温&熟成炊き機能 | 約10W | 25,000〜35,000円 |
| タイガー | ご泡火炊き JPK-G100 | 少電力炊飯&内釜3層構造 | 約12W | 30,000〜45,000円 |
| パナソニック | Wおどり炊き SR-VSX101 | AI炊飯&エコナビ搭載 | 約9W | 40,000〜55,000円 |
このように、モデルによって省エネ性能にも違いがあります。保温消費電力が10W以下のモデルは、1日中保温していても電気代が大きく跳ね上がることはありません。
機能・価格・節電効果のバランスを見て、ライフスタイルに合った炊飯器を選びましょう。
長期的に見た買い替えのメリット
古い炊飯器を長年使っていると、「まだ使えるから」と買い替えを後回しにしがちですが、実はそれがかえって電気代をムダにしている可能性もあります。
例えば、10年以上前の炊飯器と最新モデルを比べた場合、保温時の消費電力が半分以下になることもあります。
その分を新しい炊飯器の購入費に回せると考えれば、買い替えはむしろお得な投資と言えるかもしれません。
また、最近のモデルはご飯の味も進化しており、「炊きたてが前より美味しくなった!」という満足度の声も多いです。
電気代の節約に加えて、家族の食卓がもっと楽しくなるなら、これは間違いなく買い替えのチャンスです。
実際どうするのが一番お得なのか?
保温?冷凍?結局どれが一番お得なの?
家族構成やライフスタイル別に、ベストなご飯保存法をわかりやすく解説します!
保温か冷凍か、シチュエーション別の最適解
結局、ご飯は保温しておくのがいいのか、それとも冷凍した方がいいのか?
これはライフスタイルやシチュエーションによって答えが変わってきます。
例えば、朝炊いたご飯を昼や夜に食べる予定がある場合、短時間の保温(〜4時間以内)であれば、電気代もそこまで高くなく、ご飯の味もほとんど変わりません。
この場合は保温で十分です。
一方、ご飯を食べるまでに6時間以上空く、あるいは翌日以降に食べるのであれば、冷凍保存のほうが圧倒的におすすめ。
ご飯の品質を保ちやすく、電気代の節約にもつながります。
以下の表にシチュエーション別の最適な保存方法をまとめました。
| 状況 | 保温 or 冷凍 | 理由 |
|---|---|---|
| 数時間後に食べる予定 | 保温 | 味の変化が少なく、手間がない |
| 翌日以降に食べる | 冷凍 | 電気代節約+味が落ちにくい |
| 家族がバラバラに食べる | 冷凍+個別解凍 | 個別対応しやすくコスパ◎ |
| 忙しくて保存を忘れがち | タイマー+冷凍 | 自動化して節電しやすい |
| 毎食ご飯が必要 | まとめ炊き+冷凍 | 1回の炊飯で電気代節約 |
保温に頼るか冷凍を活用するかは、日々の生活スタイルを少し見直すだけで、簡単に変えることができます。
家族構成別おすすめのご飯保存方法
家族の人数や生活リズムによっても、ご飯の保存方法は変わってきます。以下に家族構成別のおすすめパターンを紹介します。
一人暮らし
・まとめて3合炊き → 1膳ずつ冷凍 → 食べたいときに電子レンジで解凍
→ 保温は基本使わず、電気代を大幅カットできます。
共働き夫婦
・ 朝タイマー炊き → 朝ごはんを食べた後、余った分は即冷凍
→ 夜ご飯は冷凍ご飯をレンチンして時短&節電。
子育て家庭(4人以上)
・朝・夜の2回に分けて炊くか、夕方に炊いて夜に食べる → 残りは小分け冷凍
→ 子ども用に「少なめパック」も作ると便利です。
高齢者夫婦
・ 少量炊飯+保温は短時間 → 食べきれる分だけ炊く習慣をつける
→ 無駄がなくなり、毎回炊きたてを楽しめます。
人数や食べる時間に合わせた保存の工夫で、電気代もご飯の品質も両方満足できる方法が見つかるはずです。
毎日のルーティンに取り入れやすい方法
節電や保存の工夫も、毎日の生活に無理なく取り入れられることが大事です。
おすすめは「ルールを1つだけ決める」こと。
たとえば、「食後すぐに余ったご飯は冷凍する」「夕飯は炊飯器のタイマーで帰宅時間に合わせて炊く」など、簡単なルールから始めてみましょう。
また、冷凍庫に「冷凍ごはんスペース」を作っておくと、保存がスムーズになります。保存容器も揃えておくと時短になり、面倒くささがなくなります。
ご飯専用タッパーを使ったり、冷凍の日付をシールで管理するのもおすすめ。
家族が多い場合は、「誰がいつどのご飯を食べるか」をざっくり分けておくと、取り合いにならずスムーズです。
何も大きく変える必要はありません。ちょっとした「習慣化」が、結果的に大きな節約と快適な食生活に繋がります。
一人暮らしと大家族で異なる考え方
一人暮らしと大家族では、ご飯の保存方法や電気代の感覚に大きな差があります。
一人暮らしの場合:
炊飯回数が少なく、1回のご飯で3〜4食分になることが多いため、冷凍保存が非常に効率的。
保温機能を使わなくても全く困らないことが多いです。
ご飯の冷凍→電子レンジ解凍という流れが定着しており、節電もスムーズに行えます。
大家族の場合:
頻繁にご飯を炊く必要があり、保温時間も長くなりがち。
電気代が積もる可能性があるため、「保温を短く・炊飯は一度にたくさん」が基本スタイルになります。
また、家族の中で「炊きたて派」と「レンジでもOK派」が混在するため、柔軟な保存方法が求められます。
家族の構成や生活リズムを考慮しながら、自分たちに合ったご飯の保存スタイルを見つけることが、無理なく続けられるコツです。
電気代を気にせず美味しくご飯を食べるコツ
最後に紹介したいのは、「電気代を気にしすぎず、でも無駄なくおいしくご飯を楽しむ方法」です。
そのためには「節電=我慢」ではなく、「工夫してムダを減らす」という考え方が大切です。
たとえば、まとめ炊き&冷凍保存をルーティンにすることで、炊飯器の稼働時間を減らし、味もキープできます。
さらに、エコモードやタイマーを使えば、電気代も抑えられます。
そして何より大切なのは、「自分にとってストレスがない方法」を見つけること。
毎日のことだからこそ、楽しさや便利さも大事にしたいですよね。
ご飯は日本人にとって主食であり、食卓の中心です。少しの工夫で、毎日もっと気持ちよく、美味しく楽しむことができます。
電気代の心配に縛られることなく、上手に炊飯器と付き合っていきましょう。
まとめ
炊飯器の保温機能はとても便利ですが、使い方次第で電気代に大きな差が出ることがわかりました。
1時間あたりの電気代は微々たるものでも、1日中つけっぱなしにしていれば、月に数百円〜年間数千円の差になることも。
また、味の変化や食品ロスにもつながる可能性があるため、「ただ保温する」から「上手に保存する」へと意識を変えることが大切です。
体験談を見ても、保温しすぎて後悔した人がいる一方で、上手にエコ保温や冷凍保存を使って節約している人もたくさんいました。
さらに、最新の炊飯器は省エネ機能が充実していて、買い替えによって電気代がぐっと抑えられるケースもあります。
自分や家族のライフスタイルに合わせて…
✅「保温」
✅「冷凍」
✅「タイマー」
などをうまく使い分ければ、無理なく節電できて、毎日のご飯もよりおいしく楽しめます。
無意識に保温しっぱなしにしていた方は、これを機に見直してみてはいかがでしょうか?
ご飯はちょっとした工夫で、もっとおいしく、もっとエコになりますよ。