
最近、「+1(800)」や「+81 80」から始まる電話番号から、中国語の自動音声が流れる不審な電話が急増しています。
突然かかってきて「请按0」などと指示されると、不安になりますよね。中には留守電にまで中国語の音声が残っていた、という報告も多く寄せられています。
このような電話は、国際的な詐欺グループによる自動発信システムであり、あなたの電話番号がどこかで流出している可能性があります。
ですが安心してください。この記事では、この電話の正体、仕組み、そして安全な対処法まで、すべてわかりやすく解説しています。
「なぜ中国語なの?」「出たら危険?」「今後どうすればいい?」という疑問を一つずつ解消し、再び安心してスマホを使えるようになるための知識をお伝えします。
この記事を読むことで、詐欺電話の正体を見抜き、自分と家族を守るための行動が取れるようになります。
不安を感じている方こそ、ぜひ最後まで読んでみてください。
+1(800)や+81 80から始まる電話番号の正体を解説

+1(800)や+81 80から始まる電話番号の正体について詳しく解説します。
それでは、順番に解説していきます。
なぜ中国語の自動音声が流れるのか
このタイプの電話で流れる中国語の音声は、ほとんどが中国系詐欺グループによる自動ダイヤルシステムによって発信されています。
詐欺グループは「ボイスボット」と呼ばれる自動通話プログラムを使い、数百万件単位で電話番号に同時発信します。音声が流れる目的は、相手が実際に電話を受けるかどうかを確認するためです。
つまり、中国語で流れる音声は「意味のある案内」ではなく、生きている番号(実際に使用されている番号)を特定するためのテストなのです。
また、日本語ではなく中国語を使う理由は、「在日中国人」や「中国語が理解できるアジア圏の人」を狙っている可能性があるためです。
日本国内でも同様の音声が報告されており、「请按0」「预约咨询」などのフレーズが共通しています。これは詐欺業者が同じテンプレートを使いまわしているためで、国際的な詐欺ネットワークの一部とみられています。
どこから発信されている可能性があるか
+1(800)はアメリカやカナダで使われるフリーダイヤル番号ですが、今回のようなケースでは番号偽装(スプーフィング)が行われています。
スプーフィングとは、実際の発信元を隠し、あたかも「正規の企業」や「国内番号」からの発信のように見せる技術です。これにより受信者が安心して電話を取ってしまうよう誘導します。
実際の発信元は、中国本土や香港、台湾などの詐欺組織の拠点からである場合が多く、VPNやボイスサーバーを経由して日本国内番号(+81)に見せかけています。
特に「+81 80」で始まる電話は、日本の携帯番号のように見えますが、海外の回線から偽装して発信されているケースが多く報告されています。
このため、見た目だけで「日本国内からの電話だ」と判断するのは危険です。
どんな内容を話しているのか
中国語の自動音声では、「预约咨询」「请按0」「请携带证件」などのフレーズが繰り返されることが多いです。これを日本語にすると「予約相談」「0を押してください」「身分証明書を持参してください」といった意味になります。
しかし、これらの内容には一貫性がなく、実際には詐欺や個人情報収集を目的としたスクリプトが流れています。
たとえば、「1を押すとサポートセンターに繋がります」「0を押すと予約が完了します」と案内されますが、これに応じると個人情報の入力やクレジットカード情報を要求されるケースがあります。
中には「日本信用情報センター」「中国大使館」などの公的機関を名乗るケースもあり、信じてしまう人も少なくありません。
この音声の目的は「操作をさせること」にあり、押した番号から通話が接続され、相手に音声データや個人情報が渡ってしまう可能性があります。
実際に出てしまった場合のリスク
もし誤って電話に出てしまっても、すぐに切れば問題ありません。
通話に出ただけで料金が発生することはありませんが、「音声案内に従って番号を押した」場合には注意が必要です。
詐欺グループは、押された番号から「この電話番号の持ち主が操作できる=実在する人間」と判断し、その番号を「有効リスト」として保存します。
その結果、今後さらに多くのスパム電話やSMSが届くようになる可能性があります。
このため、すぐにキャリアに相談し、「国際番号の着信制限」を設定しておくと安心です。
日本語での詐欺電話との違い
日本語の詐欺電話は「料金未納」「銀行口座停止」など、明確に不安を煽る内容が多いのに対し、中国語の音声詐欺は意味不明な内容で操作を促す点が特徴です。
これは、言語の壁を利用して「理解できないから押してしまう」心理を狙っていると考えられています。
また、日本語の詐欺では「個人名を呼ぶ」などの要素がありますが、中国語詐欺ではテンプレート形式で大量発信されているため、誰にでも同じ音声が届きます。
つまり、個別のターゲットというよりは、広範囲にばらまく「スパム爆撃型」の詐欺であるということです。
このような特徴を理解しておくことで、不審な電話に出ない・反応しないという正しい判断ができます。
+1(800)や+81 80から始まる電話番号の詐欺の仕組み

+1(800)や+81 80から始まる電話番号を利用した詐欺の仕組みについて詳しく解説します。
それでは、詐欺グループがどのようにして電話をかけ、どんな狙いを持っているのかを解説していきます。
スプーフィングによる番号偽装とは
「スプーフィング(Spoofing)」とは、発信元の電話番号を偽装して、まるで別の場所や人物から電話がかかってきたように見せる技術です。
詐欺グループはこの技術を使い、実際には中国本土や香港から発信しているにもかかわらず、+1(800)や+81 80などの番号を表示させて信頼を装います。
これにより、受信者が「日本の番号だから大丈夫」「企業からの電話かもしれない」と思い込み、通話を受けてしまうよう誘導します。
特にスマートフォンの画面には「東京都」「携帯電話(NTTドコモ)」などと表示される場合もあり、正規の発信者と誤認するケースが多発しています。
このような番号偽装は海外サーバーを経由して行われるため、通信キャリアでも追跡が困難なケースが多いのが現状です。
電話番号リスト流出の背景
詐欺グループは、誰にでも無作為に電話をかけているわけではありません。
実は、多くの場合はどこかから流出した電話番号リストをもとに発信しています。
このリストは、通販サイトの会員登録情報や、懸賞・アンケートサイトなどから漏れたデータがもとになっているケースが多いです。
また、SNSアカウントと電話番号を連携させている場合、悪意あるアプリや外部広告ネットワークを経由して収集されることもあります。
特に、海外の無料アプリや登録不要のサービスを利用した際に、規約に「データを第三者と共有する」と書かれていることもあり、そこから情報が流出することもあります。
このようにして集められた番号リストは、闇市場で売買され、複数の詐欺グループが使い回しているのです。
音声ガイダンス詐欺の最新手口
近年急増しているのが、機械音声を使った自動応答型詐欺(IVR詐欺)です。
これは、AIボイスや録音音声を使って「1を押してください」「0を押してください」と案内し、相手に行動を促す手口です。
特に中国語での「请按0」「预约咨询」は定型文で、操作を促すことで「本人確認ができた」と判断されるよう設計されています。
このとき、通話が一定時間継続されると、裏でシステムが通信情報を取得し、IP・機種情報・地域データを分析することがあります。
一部の悪質なケースでは、ボイスガイド後にSMSでフィッシングリンクを送付してくるパターンも確認されています。
このような手口は非常に巧妙で、相手の心理を利用して反応を引き出すのが特徴です。
海外詐欺グループのターゲット選定方法
詐欺グループは、どの番号にかけるかも戦略的に選んでいます。
まずは「生きている電話番号」をリストアップし、通話がつながった相手を「有効データ」として分類します。
その後、特定の地域(例:日本や韓国などの富裕層が多い国)を対象に、同じ音声テンプレートを使って大量発信します。
一方で、国際番号を使うと警戒されやすいため、+81で始まる日本の番号を偽装することで、信頼度を高める工夫をしています。
また、留守電設定をしている番号も重要なターゲットです。留守電に音声を残すことで、相手が「何だろう?」と再生し、不安を感じて検索するよう誘導する狙いがあります。
こうして、検索エンジン経由で「+1(800) 電話 詐欺」などのキーワードが急増し、結果的に詐欺業者の実在を拡散してしまうという皮肉な現象も起きています。
この仕組みを理解しておくことで、安易に反応しない冷静な判断ができるようになります。
留守番電話に中国語音声が入る場合の危険性

留守番電話に中国語の自動音声が入っていた場合の危険性について詳しく解説します。
それでは順番に、留守電の音声に隠された意図や危険性を見ていきましょう。
留守電を聞いただけで危険か
結論から言えば、留守番電話を聞いただけでは危険はありません。
音声を再生する行為には、通話のような通信は発生していないため、追加料金や不正アクセスが発生することはありません。
しかし、問題はその後の行動にあります。たとえば、「不安になって折り返す」「音声の指示に従って操作する」といった行動を取ると、詐欺に巻き込まれるリスクが一気に高まります。
特に「これは何だろう?」と検索して、詐欺サイトや偽サポート窓口にアクセスしてしまうケースが多く、そこで情報を抜かれることもあります。
ですので、音声を聞いた後は、必ず番号をネットで調べる前にキャリアや警察相談窓口に確認するのが安全です。
番号を押すよう促される理由
中国語音声の多くには「请按0(0を押してください)」や「请按1(1を押してください)」という案内が含まれています。
これは、相手に「操作をさせる」ことが目的です。なぜなら、ボタンを押すことで詐欺業者側が「この番号が人間によって使用されている」と判断できるからです。
通話システムでは、押された番号(DTMF信号)を検出すると、通話を続行しやすくなり、通信経路を開いたまま情報を収集できる状態になります。
その結果、「生きている番号」としてリストに保存され、今後さらに多くの詐欺電話・SMS・広告スパムが届くことになります。
つまり、指示された番号を押す行為は、詐欺グループに「あなたの存在を知らせる」行為そのものなのです。
音声内容から見る詐欺の目的
中国語の留守電音声には、一見意味の通らない文章が含まれていることが多いです。
「预约咨询请按铃」「请携带证件」など、翻訳すると「予約相談はベルを押してください」「身分証明書を持ってください」といった内容ですが、実際の意味はありません。
これらは、AI音声でランダムに組み合わされた文章であり、受信者に「何か重要なことかもしれない」と思わせる狙いがあります。
また、「日本信用情報センター」「中国大使館」「銀行」など、正式機関を装う言葉を混ぜるケースもあります。
目的は、受信者に恐怖や不安を与え、反応させることです。
不安を感じた人が思わず電話をかけ直したり、音声の指示に従って操作したりすることで、詐欺側は次のステップへと進みます。
この手法は「社会工学的詐欺」と呼ばれ、人の心理を利用して情報を引き出す手口の一つです。
個人情報の悪用リスク
このような詐欺電話に一度でも反応してしまうと、電話番号が「有効」としてデータベースに登録され、他の業者にも転売されるリスクがあります。
一部の詐欺グループは、発信者番号通知・通話時間・ボタン入力情報・地域データなどを収集し、これらを組み合わせて「個人特定プロファイル」を作成します。
その結果、次に届くスパムSMSや詐欺メールがより巧妙になり、あなたの実際の住所や名前に近い情報を使ってくるケースもあります。
さらに、スマートフォンの通話履歴がクラウド同期されている場合、同じGoogleアカウントやApple IDに紐づく他の端末(タブレットなど)にもリスクが波及します。
したがって、こうした電話を受けた後は、念のためにキャリアのサポートセンターで「不審着信履歴の削除」と「国際番号ブロック設定」を依頼しておくと安心です。
電話番号がどこで漏れた可能性があるか
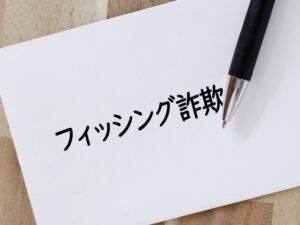
電話番号がどこから流出したのか、その可能性について詳しく解説します。
詐欺電話を受けるようになった背景には、どこかであなたの電話番号が第三者に渡ってしまった可能性があります。その主な経路を見ていきましょう。
通販サイトや会員登録情報の流出
最も多いのは、通販サイトやアカウント登録をしたサービスからの情報漏えいです。
特に、セキュリティが甘い中小規模の通販サイトでは、個人情報データベースが外部に流出する事例が後を絶ちません。
過去には、顧客リストが不正アクセスによって盗まれ、メールアドレスや電話番号が闇サイトで販売されたケースも確認されています。
また、ポイントサイトやサブスクリプション登録などで電話番号を登録していると、それらが業務委託先や関連広告会社を通じて共有されている可能性もあります。
つまり、本人が「安全」と思っている正規サイトでも、情報が意図せず拡散しているリスクがあるのです。
SNSや海外アプリ経由の情報共有
近年、電話番号が流出する大きな要因となっているのが、SNSアプリや海外製の無料アプリです。
LINEやInstagramなどの連絡先同期機能を使うと、自分の電話帳がサーバーにアップロードされ、アプリ運営側に共有される仕組みになっています。
さらに、中国製・韓国製の一部アプリには、利用規約内に「利用者データをパートナー企業に提供する」と明記されているものもあります。
このように、SNSやアプリの便利機能の裏で、本人の知らないうちに電話番号がマーケティングデータとして流通していることがあるのです。
特に無料通話アプリや翻訳アプリ、カメラアプリなどは、情報を収集する代わりに無料で提供されているケースもあります。
偽アンケートや懸賞サイトの罠
「アンケートに答えるだけでプレゼント」「抽選でギフトカードが当たる」といった懸賞サイトや広告は、情報収集目的で作られていることがあります。
このようなサイトでは、氏名やメールアドレスのほかに「電話番号必須」と記載されている場合があります。
実際には抽選も行われず、入力された情報はリスト化され、スパム業者に販売されてしまうのです。
中には、「Googleフォーム風」や「LINE登録風」に見せかけた偽ページも存在し、一般のユーザーが気づかずに入力してしまうケースも少なくありません。
このようなサイトでは、応募完了後にSMSが届くことがあり、そこからさらに詐欺サイトへ誘導される流れが確認されています。
スパム業者によるデータ売買
個人情報が一度でも漏れてしまうと、その後は「データブローカー」と呼ばれる業者によって売買されます。
これらの業者は、電話番号・メールアドレス・年齢層・地域などの情報を「マーケティングリスト」として販売しています。
詐欺グループはこのリストを購入し、同じテンプレートの音声を使って大量発信を行うのです。
つまり、今回あなたに届いた「中国語の音声電話」も、どこかで入手したリストに含まれていた可能性が高いということです。
また、こうしたデータは一度流出すると削除されることがなく、何年も使い回され続ける傾向があります。
したがって、今後同じような電話が繰り返し届く可能性があるため、着信拒否設定や電話番号変更の検討も必要になります。
+1(800)や+81 80から始まる電話番号への対処法5つ

+1(800)や+81 80から始まる不審電話への具体的な対処法を5つ紹介します。
ここでは、知らない番号からの中国語音声電話に対して、どう行動すれば安全かを具体的に解説します。
電話に出ない・折り返さない
最も基本であり、最も効果的な対策は電話に出ない・折り返さないことです。
見知らぬ番号、特に「+」から始まる国際番号や「080」「050」「0120」など一見国内っぽく見える番号であっても、発信元を確認できない場合は応答しないのが鉄則です。
特に、中国語・英語など日本語以外の音声が流れた場合は、すぐに通話を終了しましょう。
詐欺電話は、通話時間が長いほど情報を収集されるリスクが高まるため、反応しないことが最大の防御になります。
また、折り返し電話をかけると、海外接続料金が発生する場合もあるため、金銭的リスクも伴います。
キャリアの迷惑電話ブロックを利用する
ドコモ、au、ソフトバンクなどの主要キャリアには、迷惑電話を自動で検知・拒否する機能があります。
たとえば、ドコモなら「あんしんセキュリティ」、auなら「迷惑電話撃退サービス」、ソフトバンクなら「迷惑電話ブロック」といったサービスです。
これらを有効化しておけば、スパム発信として登録されている番号からの着信は自動的にブロックされます。
特に「海外からの着信を制限」する設定を有効にすると、+1や+86など海外プレフィックスを持つ番号を防げます。
アプリによっては着信時に警告表示が出るものもあるので、常に最新状態にアップデートしておくことが大切です。
国際電話着信を制限する設定を行う
スマートフォンの設定やキャリア契約のオプションで、国際電話からの着信を制限できます。
これは特に有効な手段で、詐欺電話の多くは海外サーバーを経由して発信されているため、根本的な防御になります。
以下は代表的な設定例です。
| キャリア | 設定方法 |
|---|---|
| ドコモ | あんしんセキュリティ→通話→海外番号ブロックON |
| au | 迷惑電話対策アプリ→海外発信制限を有効化 |
| ソフトバンク | My SoftBank→通話設定→国際発着信制限 |
この設定をすることで、「+1」「+81」「+86」などから始まる電話をすべて遮断できるため、不安な人には特におすすめです。
不審番号を通報する方法
不審な番号は、自分だけで抱え込まずに、公式の相談窓口へ報告しましょう。
日本では以下の機関が迷惑電話や詐欺被害に対応しています。
| 通報先 | 内容 |
|---|---|
| 警察相談専用ダイヤル「#9110」 | 詐欺電話・不審通話の相談 |
| 総務省 消費者ホットライン「188」 | 通信トラブルや架空請求 |
| 各キャリアのサポート窓口 | 迷惑電話のブロック・記録削除 |
また、Googleなどの検索結果に「迷惑電話」として登録されるよう、口コミサイト(電話番号検索サービス)に情報を共有することも被害拡大防止になります。
セキュリティアプリで端末を保護する
スマートフォンには、通話やSMSの監視機能を備えたセキュリティアプリを導入することをおすすめします。
特におすすめなのは、以下のようなツールです。
| アプリ名 | 主な特徴 |
|---|---|
| トゥルーコーラー(Truecaller) | 全世界のスパム番号データベースを自動照合 |
| ノートンモバイルセキュリティ | 不審SMS検知・迷惑通話ブロック・URL保護 |
| カスペルスキー モバイル | 詐欺リンク検出・通話ブロック・端末保護 |
これらのアプリを入れておくと、着信時に「詐欺の可能性があります」などの警告が表示されるため、詐欺電話を事前に防げます。
また、詐欺通話やSMSを誤って開いてしまった場合でも、感染防止やデータ保護の機能が働くため安心です。
安心できるための今後の対策と心構え
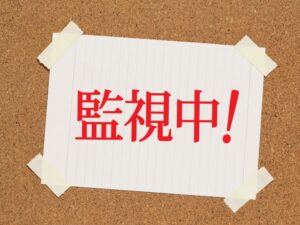
+1(800)や+81 80から始まる電話への不安を減らし、今後の被害を防ぐために取るべき行動と心構えについて解説します。
ここでは、日常生活の中でできる安全対策や、意識しておきたい行動についてお話しします。
不明な番号は検索してから判断する
知らない番号から着信があった場合は、まず出ずに番号を検索してみましょう。
検索エンジンに電話番号を入力するだけで、多くの場合は「迷惑電話」「詐欺」「スパム」などの情報が表示されます。
また、番号検索専用サイト(例:「迷惑電話番号サーチ」「電話帳ナビ」など)を利用すれば、他の人の被害報告も確認できます。
注意点として、検索結果に「中国語の自動音声」など同じような被害が多数報告されている場合、その時点で詐欺電話と判断して問題ありません。
つまり、「疑わしい」と感じたら出ないという判断が、最も安全な選択肢です。
家族や高齢者にも注意を呼びかける
このような電話詐欺の被害は、特に高齢者や海外経験の少ない人に多く見られます。
なぜなら、国際番号や外国語の音声に慣れておらず、焦って操作してしまう傾向があるからです。
そのため、家族や身近な人にも「不明な電話には出ない」「番号を押さない」「不安なら家族に相談」というルールを共有しておくことが大切です。
また、実際に被害にあった場合でも、恥ずかしがらずに家族や警察に相談できるような環境づくりが重要です。
電話詐欺は「心理的に追い詰める」ことを目的にしているため、冷静に対応するためにも家族の協力体制を整えておきましょう。
電話以外の詐欺(SMSやメール)にも警戒する
最近では、電話だけでなくSMSやメールを利用した詐欺も増加しています。
電話番号が漏れた場合、その番号を使ってSMS経由で「荷物の不在通知」や「アカウント停止のお知らせ」などの偽メッセージが届くことがあります。
これらのメッセージには必ずリンクが含まれており、アクセスすると個人情報入力ページへ誘導される仕組みです。
こうしたケースでは、たとえ日本語であっても注意が必要です。内容が「重要」や「至急」と書かれていても、まずは公式アプリや公式サイトから確認するようにしましょう。
リンクを直接タップせず、検索エンジン経由で公式サイトにアクセスするのが安全です。
定期的に情報漏えいチェックを行う
最後に、自分の電話番号やメールアドレスが流出していないか、定期的にチェックすることをおすすめします。
信頼できるサービスとしては、「Have I Been Pwned(英語サイト)」や「情報漏えいチェッカー.jp」などがあります。
これらにメールアドレスや電話番号を入力すると、過去にデータベース流出に含まれていたかを確認できます。
もし流出が確認された場合は、登録しているサイトのパスワード変更、不要なアカウントの削除を行いましょう。
また、セキュリティ意識を高めるために、年に数回はスマホの設定見直しやアプリ権限の整理を行うと安心です。
詐欺グループは人の油断を突いてきます。日々の小さな警戒が、自分と家族を守る最善の対策です。
まとめ|+1(800)や+81 80から始まる電話は詐欺の可能性が高い
| 主な項目 | 内容・ページ内リンク |
|---|---|
| 中国語の自動音声が流れる理由 | なぜ中国語の自動音声が流れるのか |
| 番号偽装の仕組み | スプーフィングによる番号偽装とは |
| 留守電を聞く危険性 | 留守電を聞いただけで危険か |
| 電話番号流出の原因 | 通販サイトや会員登録情報の流出 |
| 安全な対処法 | 電話に出ない・折り返さない |
+1(800)や+81 80から始まる電話番号から、中国語の自動音声が流れる着信は、ほぼ確実に詐欺グループによるものです。
これらの電話は、国際的なスパムネットワークを利用して発信されており、あなたの電話番号がどこかで漏れたことを意味しています。
ただし、留守電を聞いただけで被害が発生することはありません。問題は、その後に折り返したり、音声の指示に従って操作してしまうことです。
今後同じような電話を防ぐには、キャリアのブロック機能を使い、国際番号の着信を制限することが有効です。また、不審番号は必ず通報して、他の人の被害を防ぐ意識も大切です。
さらに、アプリや通販サイトなどに登録している電話番号を定期的に見直し、不要なアカウントを削除することで、流出のリスクを下げられます。
「知らない番号には出ない」この一つの意識が、あなたを詐欺から守る最も強力な盾になります。
参考リンク:総務省|詐欺電話対策ガイド
参考リンク:警視庁|特殊詐欺・不審電話への注意








