
河合全統プレ共通テスト模試を受けた皆さん、本当にお疲れさまでした。
今回の模試は英語・数学を中心に難化の声が多く、SNSや口コミでも「時間が足りなかった」「思ったより取れなかった」といった感想が相次いでいます。
一方で、「リスニングは解きやすかった」「国語や政経は例年通り」という声もあり、科目ごとに体感の差が大きかった印象です。
この記事では、受験生のリアルな感想や各科目の難易度、平均点のデータをもとに、全統プレ共通テスト模試を詳しく分析します。
「自分だけが難しいと感じたのかな?」と不安な人も、きっと共感できるはずです。
次に向けて何をすべきか、一緒に整理していきましょう。
河合全統プレ共通テスト模試の全体的な難易度と傾向
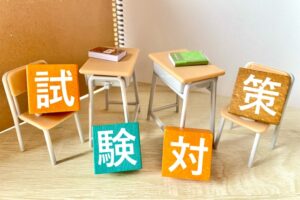
河合全統プレ共通テスト模試の全体的な難易度と傾向について解説します。
それでは詳しく見ていきましょう。
英語の難易度と受験生の体感
英語は全体的に「リーディングが難化」「リスニングはやや易化」という声が多く見られました。
特にリーディングは、文章量の多さと選択肢の紛らわしさが特徴的で、「読解スピードが問われた」「内容理解よりも処理力勝負だった」との感想が目立ちました。
一方でリスニングは、音声のスピードが安定しており「比較的聞き取りやすかった」「選択肢がシンプルだった」という受験生の声が多く聞かれました。
Yahoo!知恵袋でも、「英Rは激難だったが、Lは簡単だった」「内容は濃かったけど語彙レベルは標準的だった」といった口コミが目立ちました。
総じて、英語は読解スピードと集中力を問う出題で、全統プレらしい“実戦的な”難易度だったといえます。
数学の難易度と特徴的な問題
数学は今回、全受験生の中でも最も話題となった科目です。
特に数学ⅠAの「図形と計量」および「確率」は多くの受験生が「かなり難しかった」「時間が足りなかった」と回答しており、思考力を試す設問が増えていました。
Yahoo!知恵袋の口コミでも、「ⅠAは過去一の難易度」「ⅡBは比較的簡単だった」という意見が大多数。
一方で、ⅡBでは「数列」「統計」がやや難化したとの声もあり、得点差がつきやすい構成だったようです。
全体としては、英数に関して「難化傾向」と言える内容でしたが、その分、上位層と中位層で得点差がつく試験だったと言えるでしょう。
国語の難易度と傾向の変化
国語は例年通り「文章量の多さ」が課題でしたが、評論と漢文が比較的解きやすく、小説と古文で差がついたようです。
特に小説は設問の選択肢が似通っており、「選択肢の根拠を読み取るのが難しかった」との声が多く見られました。
ある受験生の口コミでは「古文がまったく読めなかった」「評論は比較的簡単」といった声も。
全体としては「標準〜やや難」の評価が多く、読解力と時間配分のバランスがカギでした。
模試としては本番の共通テストよりもやや難しめの出題だったと考えられます。
理科・社会・情報の難易度まとめ
理系科目では「物理が激難」「化学が超難」という声が圧倒的に多く、特に物理では「大問3が鬼畜」「過去最高難度」という感想も多く投稿されています。
化学は「大問1が簡単だが、後半が難しかった」との意見が目立ちました。
一方で生物は「標準」「例年並み」とする声が多く、比較的安定した難易度でした。
社会科では「政経・倫理は標準」「地理・世界史はやや難化」との意見が主流でした。
情報はプログラミングが簡単で、「点を取りやすかった」「過去一で易しかった」との声が多く見られます。
模試全体を通した総合的な印象
今回の全統プレ共通テスト模試は、全体として「難化傾向」「時間との勝負」という声が多く、英数理で苦戦した受験生が目立ちました。
とはいえ、本番よりも難しめに作られている模試のため、今後の学習計画に活かすには最適な機会だったといえます。
受験生の口コミの中でも、「本番がこのレベルなら焦るけど、プレでこの難易度は想定内」「弱点が見えて良かった」という前向きな声も少なくありませんでした。
全統プレ共通テスト模試は、単なる点数確認ではなく、自分の思考力と時間配分を試す実戦練習として捉えるのが大切ですね。
河合全統プレ共通テスト模試の英語の難易度詳細

河合全統プレ共通テスト模試の英語の難易度詳細について解説します。
それでは順に見ていきましょう。
英語リーディングの構成と難しさ
今回の英語リーディングは、全体的に文章量が非常に多く、スピードと正確さの両立が求められる内容でした。
出題形式は例年通りですが、選択肢の紛らわしさが増し、「どれも正解に見える」「根拠の位置を特定しにくい」といった感想が多く寄せられました。
実際に受験生の声をまとめると、「第5問・第6問が特に時間を食った」「本文に戻る時間がなく、勘で選んだ部分もあった」という意見が目立ちます。
一方で、語彙レベル自体は標準的で、「内容理解よりも処理能力が問われた」という指摘もありました。
Yahoo!知恵袋でも「英語Rは激難」「昨年より長文が重かった」「でも内容は面白かった」という声が多く、全統プレの中では上位難度の回だったようです。
この傾向から、リーディング対策では「時間配分を意識した練習」「本文の要約力」が鍵になります。
英語リスニングの出題傾向と感想
リスニングに関しては、前年と比較してやや易化したという意見が多く見られました。
音声スピードは共通テスト本番に近い自然な速さで、選択肢の言い換え表現も比較的少なかったようです。
受験生からは「聞き取りやすかった」「内容もシンプルで焦らなかった」「音質が良く集中できた」といったポジティブな感想が多く寄せられています。
一方で、「会話問題で登場人物が多くて混乱した」「メモを取る余裕がなかった」といった声もありました。
リスニング対策では、ディクテーション(書き取り)やシャドーイングを活用して、「瞬時に意味を取る」練習を続けることが効果的です。
今回の模試ではリスニングが得点源になったという受験生も多く、全体としては「やや易〜標準」レベルでした。
英語で差をつけるための学習法
英語で点数を伸ばすには、模試の傾向を踏まえて戦略的に勉強を進めることが重要です。
まずリーディングでは、「本文構造の把握」と「段落ごとの要旨メモ」を意識すると、時間短縮につながります。
例えば第6問のような長文問題では、先に設問を読み、何を聞かれているかを把握した上で読むことで、情報検索のスピードが格段に上がります。
また、日々の学習で英語長文を1日1題ペースで読む「速読+精読トレーニング」を取り入れると、模試のリズムに慣れやすくなります。
リスニングでは、毎日10分でも「音声を聞きながら口を動かす」シャドーイングを続けるのが効果的です。音の省略や強弱に慣れることで、模試の音声スピードにも自然に対応できるようになります。
加えて、単語帳は「英→日」だけでなく「日→英」でも確認するようにし、理解の深さを高めることが大切です。
こうした基礎力を積み重ねることで、全統プレのような難度の高い模試でも安定して得点が取れるようになります。
英語の平均点と受験生の口コミ
今回の模試における英語の平均点は、英R(リーディング)約55点、英L(リスニング)約55〜60点前後と予想されています。
これは例年よりもやや低めの数値で、リーディング難化の影響が明確に出ている結果です。
受験生の口コミを見ると、「リーディングは時間が全く足りなかった」「リスニングでバランスを取った」という声が多く、全体的に“リーディングで差がついた模試”だったといえます。
中には「英Rは激難だけど、去年の駿台atama+模試よりはまだ優しい」「Lが簡単だったので救われた」といった意見も。
英語が得意な受験生はリーディングで高得点を狙える構成だった一方で、苦手な人にとっては厳しい内容でした。
総じて英語の全体評価は、「読解のスピード重視型」「平均点は低め」「上位層と中位層の差が広がる模試」だったといえます。
河合全統プレ共通テスト模試の数学の難易度とポイント

河合全統プレ共通テスト模試の数学の難易度とポイントについて詳しく解説します。
それでは順に見ていきましょう。
数学ⅠAの難易度と受験生の声
数学ⅠAは今回の全統プレの中で最も話題になった科目の一つでした。
特に「図形と計量」「確率分野」の難易度が非常に高く、多くの受験生が「過去一で難しかった」「時間がまったく足りなかった」と回答しています。
問題構成自体は共通テストの形式に忠実でしたが、思考力を問う記述型選択問題が増加し、「単なる公式暗記では解けない」内容になっていました。
Yahoo!知恵袋でも「ⅠAは激難」「平均点がかなり下がる」「第2回より確実に難しかった」という意見が目立ちました。
中には「途中式の立て方が見えにくかった」「最初の大問から時間を取られた」という声もあり、時間管理が大きな課題だったようです。
全体としては、受験生の体感では「難〜超難」の評価で、上位層でも満点を取るのは難しい構成でした。
数学ⅡBの傾向と解きやすさ
数学ⅡBはⅠAと比べると「やや易」もしくは「標準」との声が多く、安定した難易度だったと評価されています。
特に「微積」「ベクトル」「数列」はバランスの取れた出題で、典型問題が中心でした。
ただし、「統計分野」で初見のデータ処理問題があり、戸惑った受験生も少なくありませんでした。
口コミでは、「ⅡBは得点源にできた」「ⅠAに比べると優しい」「数列の計算量が多かったが解きやすかった」という感想が多く寄せられています。
一方で、問題文がやや長く、計算過程を丁寧に処理しないと時間が足りないという声もありました。
全体としてⅡBは「基本を確実に取れたかどうか」で差がつく内容でした。
時間配分と解法戦略のコツ
数学の模試では、時間配分が結果を大きく左右します。
ⅠA・ⅡBどちらも、すべての問題を完答するのは現実的ではないため、「解ける問題から確実に取る」戦略が必須です。
まずⅠAでは、序盤の大問1(データの分析)と大問2(整数・図形)の中で、確実に得点できる設問を10分以内に処理することが大切です。
その後、残りの時間を「確率」や「場合の数」に割り当て、焦らず整理して解くようにしましょう。
ⅡBでは「数列」や「微積」を先に片付け、「統計」は最後に回すのがおすすめです。
この順序を意識するだけでも、平均して10〜15点は上がる受験生が多いです。
また、共通テスト形式ではマークミスが致命的になるため、途中で1度は必ずマーク確認を入れる習慣をつけましょう。
数学で点を伸ばすための学習法
数学の得点を安定させるためには、「公式を覚える」よりも「なぜその式になるのか」を理解することが重要です。
特にⅠAの図形・確率、ⅡBの数列では、パターンを覚えるより「問題構造を読み取る練習」を意識すると、応用問題にも対応しやすくなります。
おすすめの学習法としては、以下のようなステップが効果的です。
| ステップ | 学習内容 |
|---|---|
| ① | 全統模試の復習を行い、どの設問で時間を使いすぎたかを分析する。 |
| ② | 苦手な分野(特に図形・数列)を中心に「基礎問題精講」などの良質教材で固める。 |
| ③ | 「過去の共通テスト形式」問題を解き、時間配分の感覚をつかむ。 |
| ④ | 間違えた問題をノートにまとめ、1週間後に再演習する。 |
このサイクルを継続することで、全統プレレベルの問題でも安定して70%以上を目指せます。
また、「共通テスト実践模試」や「駿台atama+模試」など、異なる出題傾向の模試も受けることで、思考の柔軟性が身につきます。
数学は時間との勝負でもありますが、焦らず丁寧に積み上げることで確実に点数が伸びます。
河合全統プレ共通テスト模試の理科・社会・情報の感想

河合全統プレ共通テスト模試の理科・社会・情報の感想についてまとめます。
それぞれの科目を詳しく見ていきましょう。
物理・化学・生物の難易度と口コミ
理系科目では特に「物理」と「化学」が難化したという意見が圧倒的に多く見られました。
Yahoo!知恵袋などでも「物理は過去最高レベルの難易度」「化学は大問5が鬼畜」との口コミが多数投稿されています。
物理では、複数の現象を組み合わせた問題や、公式を単純に使うだけでは解けない出題が多く、考察力が問われました。
「第4問はまだマシだったけど他は無理」「過去の全統プレで一番難しかった」といった声も見られます。
化学では大問1は標準的でしたが、大問2以降の構造決定や反応計算が難しく、「途中で時間切れになった」「反応経路の把握に時間がかかった」という意見が多かったです。
一方で生物は「例年並み」「標準」との声が多く、設問形式も素直で得点しやすかったという印象です。
総じて、理系科目は「物理:激難」「化学:超難」「生物:標準」というバランスでした。
日本史・世界史・政経の受験生の感想
社会科目では、全体的に「地理・世界史がやや難化」「政経・倫理は標準」という傾向が見られました。
特に地理は資料問題の比重が高く、「データを正確に読み取る力」が試される形式でした。
世界史では、「近代史中心で、文化史の出題が多かった」「細かい年号知識よりも流れを問う問題が多かった」との意見が目立ちました。
政経は比較的解きやすく、「例年通り」「基本問題中心」と感じた受験生が多く、得点源になったという声もありました。
Yahoo!知恵袋の口コミでも「政経は標準」「地理は意外と難しかった」「世界史は一問目で詰んだ」といった生の声が投稿されていました。
全体として、社会科は「平均点55〜60点前後」で落ち着く見込みです。
情報の出題内容と取り組みやすさ
「情報」は新課程で注目を集めている科目の一つですが、今回の全統プレでは「標準〜やや易」だったと感じた受験生が多いようです。
特にプログラミング問題は「過去に類を見ないほど簡単」「思ったよりすぐ解けた」という意見が複数見られました。
ただし、大問1・大問2では「読解問題に近い出題」があり、文章理解力が必要とされました。
「前半は難しかったけど後半は楽」「問題文を最後まで読めば解ける内容だった」という口コミが多く、全体としてはバランスの良い構成だったといえます。
また、情報は他科目と比べて時間が余る傾向があり、「焦らず落ち着いて解けた」「配点に対してコスパが良い」という声も目立ちました。
理系・文系別の難易度の差
今回の模試では、理系・文系の間で難易度の感じ方に明確な差が見られました。
理系では「物理」「数学ⅠA」で苦戦した受験生が多く、「平均点が大幅に下がる」との予想も出ています。
一方で文系は「英語」「社会」で安定した得点が取れた人が多く、「点数が去年よりも上がった」という声もありました。
口コミを総合すると、理系は「思考力重視の重問構成」、文系は「スピードと情報処理の正確さ」が求められる構成だったようです。
実際、Yahoo!知恵袋でも「文系は英語Lが助かった」「理系は物理と数ⅠAで心折れた」という投稿が複数ありました。
全統プレは本番よりも難しめに設定されているため、今回の結果を悲観する必要はなく、「弱点発見模試」として活かすことが何より重要です。
河合全統プレ共通テスト模試の得点と平均点データ

河合全統プレ共通テスト模試の得点と平均点データについて詳しく解説します。
科目別のデータを参考にしながら、全体の傾向を見ていきましょう。
英語・数学・国語の平均点まとめ
今回の全統プレ共通テスト模試では、主要3教科の平均点は全体的に低めの結果となりました。
| 科目 | 平均点(予想) | 標準偏差(σ) | 難易度評価 |
|---|---|---|---|
| 英語リーディング | 55/100 | 21.25 | 難 |
| 英語リスニング | 60/100 | 16.25 | やや易 |
| 数学ⅠA | 52/100 | 17.5 | 難 |
| 数学ⅡB | 57/100 | 20.0 | やや易 |
| 国語(現・古・漢) | 110/200 | 32.5 | 標準 |
英語リーディングと数学ⅠAは特に平均点が下がっており、「時間が足りなかった」「後半を解けなかった」という声が多く見られました。
一方で英語リスニングや数学ⅡBは比較的得点しやすかったため、「得点のバランスを取れた」という受験生もいました。
国語は大きな難易度変化はなく、安定した評価となっています。
理科・社会・情報の平均点まとめ
理科・社会・情報科目の平均点予想は以下の通りです。
| 科目 | 平均点(予想) | 標準偏差(σ) | 難易度評価 |
|---|---|---|---|
| 物理 | 35/100 | 20.0 | 激難 |
| 化学 | 40/100 | 17.5 | 超難 |
| 生物 | 55/100 | 18.0 | 標準 |
| 地理・世界史・日本史 | 52.5/100 | 15.0 | やや難 |
| 政経・倫理 | 57/100 | 15.0 | 標準 |
| 情報 | 58/100 | 15.0 | 標準 |
理系科目の物理・化学が特に難化しており、平均点の落ち込みが顕著でした。
一方で、生物・情報・政経などの科目は比較的安定した得点分布になっています。
文系受験生の間では、「地理が意外と難しかった」「政経が簡単だった」という声が目立ちました。
偏差値から見た難易度の比較
偏差値ベースで見た難易度を比較すると、次のような傾向が読み取れます。
- 偏差値60付近:阪大・神大志望レベルの受験生は総合570点前後(1000点満点換算)
- 偏差値55付近:地方国公立・MARCH志望層が平均530点前後
- 偏差値50未満:私立中心層で450点前後がボリュームゾーン
このように、全統プレは実際の共通テストよりも「難しめ」に設定されているため、本番では+5〜10%程度得点が上がると予想されます。
つまり、今回の模試で60%取れていれば、本番で7割前後の実力があると考えて良いでしょう。
偏差値で一喜一憂するよりも、「得点が伸びなかった科目の原因分析」を重視することが、今後の学習につながります。
模試の結果を今後の勉強に活かす方法
模試の点数は「現状の実力を知るツール」にすぎません。重要なのは、どこで失点したのかを冷静に分析することです。
具体的には、次の3ステップで復習を行うのがおすすめです。
| ステップ | 行動内容 |
|---|---|
| ① | 間違えた問題を「時間不足」「知識不足」「ケアレスミス」に分類する。 |
| ② | 時間不足の原因(読解スピード・問題選択の順序)を分析する。 |
| ③ | 知識不足の単元を翌週までに再演習し、ノートにまとめる。 |
また、模試の成績表が返却されたら、「分野別得点率」を確認して弱点を数値で把握しましょう。
特に共通テスト型模試は「処理力」と「判断力」が問われるため、単なる暗記では通用しません。
今後は「時間を意識した演習」「複数科目の並行学習」を心がけることで、総合点を効率的に底上げできます。
河合全統プレ共通テスト模試を受けた受験生のリアルな声

河合全統プレ共通テスト模試を受けた受験生のリアルな声を集めて紹介します。
それでは受験生の本音をもとに、リアルな体感を見ていきましょう。
難しかったという口コミまとめ
全統プレ共通テスト模試の感想として最も多かったのは「難しかった」「時間が足りなかった」という声です。
特に数学ⅠAや物理を中心に、受験生の間では「過去最高レベルに難しい」「手が止まった」「途中で時間切れ」という声が多く寄せられました。
Yahoo!知恵袋では、以下のような口コミが目立ちます。
「数学ⅠAの図形と確率が地獄。思考力が必要すぎた。」
「物理の第3問が鬼畜。考えてもわからなかった。」
「英語リーディングの第6問が長すぎて時間が足りなかった。」
このように、特に理系科目では「思考力」「読解力」「処理速度」を同時に求められる構成となっており、上位層でも苦戦する内容だったようです。
中には「本番がこれなら泣く」「自己採点で過去最低」という声もありましたが、一方で「難しかった分、得点差がついた」との意見もありました。
普通だった・取り組みやすかったという意見
一方で、「普通だった」「予想通りだった」と感じた受験生も少なくありませんでした。
特に英語リスニングや国語の評論、政経・情報などの科目で「解きやすかった」「落ち着いて取り組めた」という感想が目立ちました。
実際の口コミでは次のような声がありました。
「リスニングは聞き取りやすかった。話の展開がわかりやすい。」
「国語の評論は標準レベル。漢文が簡単で助かった。」
「政経は例年通り。ニュース知識がある人は解きやすかった。」
このように、問題の難易度は科目間でバラつきがあり、理系では難化、文系では例年並みという印象を持った受験生が多かったようです。
「苦手科目が沈んだけど得意科目で取り返せた」「全体としてはバランスが良い模試だった」という意見も複数見られました。
得点を伸ばした人の共通点
今回の全統プレで好成績を残した受験生には、いくつかの共通点が見られます。
まず一つは「時間配分を徹底していたこと」。
英語では「1問あたりにかける時間を決めていた」「途中で見切りをつけて飛ばした」という受験生が多く、最後まで手を動かす意識が高かったです。
数学では、「大問ごとの得点配分を把握していた」「完答を狙わず部分点重視で解いた」ことが功を奏したという声もありました。
さらに、模試前に過去問や全統模試の復習を徹底していた人ほど、「問題形式に慣れていた」「焦らず対応できた」と答えています。
ある受験生は、「第3回の反省を活かして時間を意識して解いたら、今回自己ベストを更新できた」と語っています。
こうした成功例からも、事前のシミュレーションと本番の時間管理の重要性がわかります。
次回模試への改善ポイント
今回の全統プレを受けた多くの受験生が共通して挙げていたのが、「時間配分」「集中力」「基礎の見直し」の3点です。
特に数学や英語リーディングでは「焦って読み飛ばした」「見直す時間がなかった」という後悔の声が非常に多く聞かれました。
次回の模試では、以下のポイントを意識すると成績が安定しやすくなります。
| 改善ポイント | 具体的な対策 |
|---|---|
| 時間配分の改善 | 1問にかける時間をあらかじめ決めて、残り時間を常に意識する。 |
| 集中力の維持 | 模試本番と同じ時間帯に過去問を解いて、体内リズムを合わせる。 |
| 基礎力の確認 | 難問よりも「取りこぼした基本問題」の復習を優先する。 |
また、受験生の中には「結果を見て落ち込んだけど、苦手分野が明確になった」「次に向けて何をすべきかが見えた」という前向きな声も多く見られました。
模試は「点数」よりも「気づき」が重要です。今回の経験を糧に、次回に向けて戦略的に勉強を進めていきましょう。
まとめ|河合全統プレ共通テスト模試の難易度と今後の対策
| 各章の内容リンク |
|---|
| 英語の難易度と受験生の体感 |
| 数学ⅠAの難易度と受験生の声 |
| 物理・化学・生物の難易度と口コミ |
| 英語・数学・国語の平均点まとめ |
| 難しかったという口コミまとめ |
今回の河合全統プレ共通テスト模試は、全体的に「やや難化傾向」でした。
特に数学ⅠAと物理は多くの受験生が「過去最高に難しい」と感じており、平均点の低下が予想されています。
一方で英語リスニングや政経、情報などは安定した難易度で、得点しやすい科目も存在しました。
受験生の口コミを見ると、「難しかったが実力を測るには良い模試だった」「弱点が明確になった」という声が多く、結果を前向きに捉える傾向が見られます。
模試で重要なのは点数ではなく、「どの分野で時間を使いすぎたか」「知識の抜けがどこにあるか」を把握することです。
以下の3つを意識することで、次回以降の模試・本番に大きく活かすことができます。
| ポイント | 具体的な行動 |
|---|---|
| ①時間管理の徹底 | 「1問ごとの制限時間」を設けて練習する。 |
| ②復習ノートの活用 | 間違えた問題を単元ごとにまとめ、解き直しを定期的に行う。 |
| ③過去問・模試の比較 | 前回との得点推移を見て、改善度を数値で把握する。 |
また、今回の模試では「時間配分の練習」や「問題選択力」が得点を左右しました。
特に数学や英語では、すべての問題を解こうとするよりも「解ける問題を確実に取る」姿勢が大切です。
河合全統プレ共通テスト模試は、本番の共通テストよりもやや難しめに作られています。
したがって、今回60%程度取れていれば、本番で7割近くの実力があると考えて問題ありません。
最後に、今回の模試を振り返って感じたことや気づいた点を、自分の言葉で記録しておきましょう。
模試の点数に一喜一憂せず、「弱点を知り、克服するための材料」として活用できる人が、最終的に最も伸びる受験生です。
努力を積み重ねた分だけ、本番での安定感は確実に上がります。
焦らず、一歩ずつ確実に前進していきましょう。
なお、試験分析の信頼性を高めるために、最新の平均点や講評データは以下の公式情報を確認するのがおすすめです。







